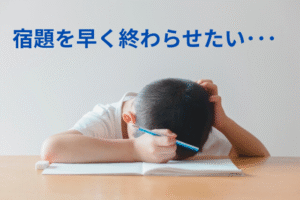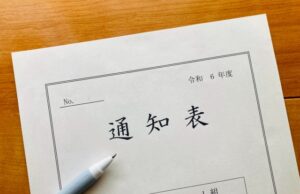こんにちは。たかみやです。
中学生ともなると、部活や友達との遊び、また塾通いに忙しく、勉強が後回しになること、ありますよね。
我が家も同じです。塾に通わせず家庭学習で頑張っているので、子どもだけに任せるのではなく、親が勉強に関心を持ち、深く関わることが大切だと感じています。
でも、どうやって?そう思いますよね。
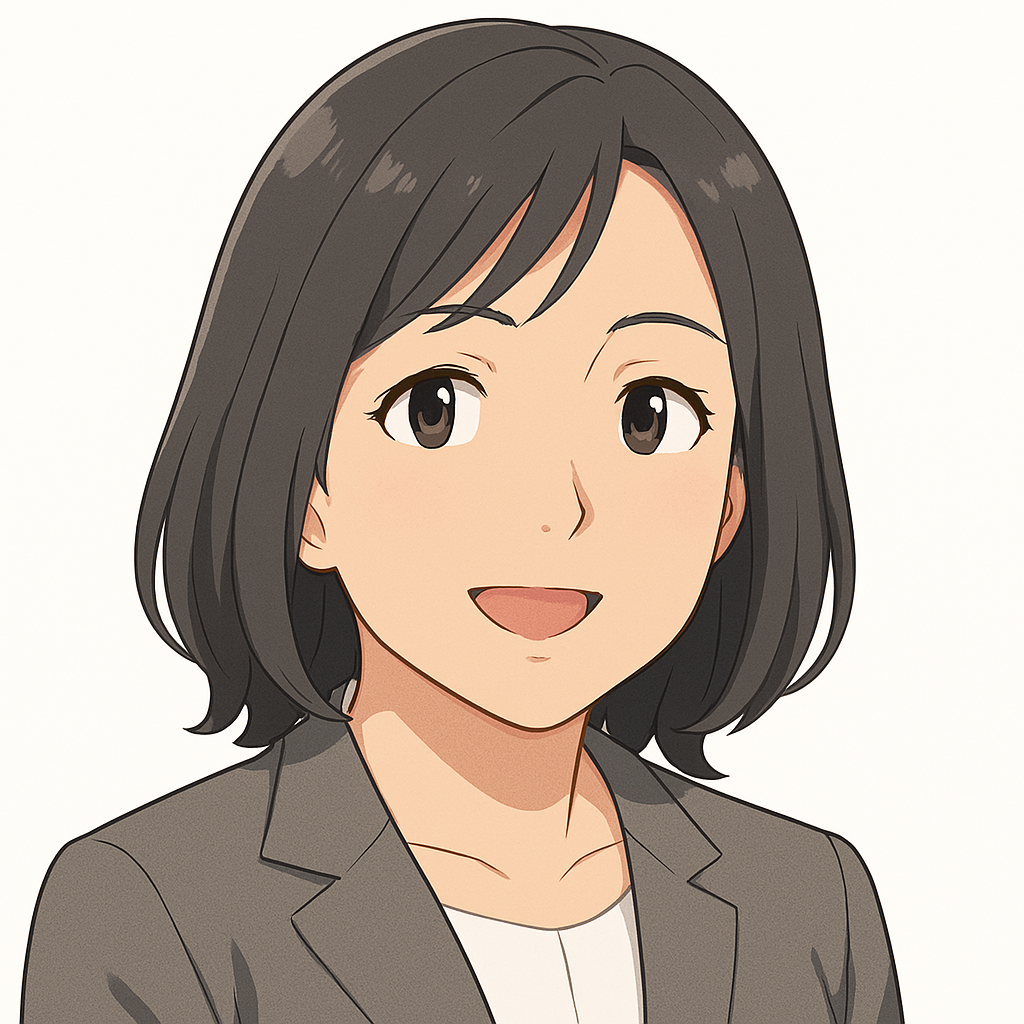 たかみや
たかみや今回は、私が実際に試して効果があった、家庭学習で親ができる効果的な関わり方を3つご紹介します。
1. 勉強の「準備」をなくす工夫をする


勉強を始めるまでに、筆記用具を探したり、ワークを探したり…といった「準備」に時間がかかると、せっかくのやる気も半減してしまいます。
そこで、勉強に取り掛かるまでの時間を最小限にするための工夫をしましょう。
勉強道具の配置を見直す
我が家では、リビングで学習するので、勉強道具は全てリビングに置きっぱなしです(リビングは片付きませんが…)。こうすることで、いつでもすぐに勉強に取り掛かれる環境を作りました。
今日やることを先に準備しておく
子どもが小学生の時は、毎日やるページを開いて、鉛筆と消しゴムを机に置いていました。高学年になると、今日勉強するプリントをファイルに挟んでおき、「このファイルから始めればいいよ」と声をかけるようにしていました。
2. 間違えた問題で「叱らない」


ついつい「なんでできないの?」と言いたくなりますが、ここはぐっとこらえましょう。
勉強で間違えることは、決して悪いことではありません。むしろ「できるようになるチャンス」と捉えることが大切です。
一緒に原因を探す
もし子どもが間違えていたら、「どうすれば次は間違えないかな?」と一緒に考えてみましょう。親が答えを教えるのではなく、子ども自身に考えさせることが重要です。
ポジティブな声かけを心がける
子どもが間違えて落ち込んでいる時は、「できなかったことができるようになるチャンスが来たよ」と前向きな言葉をかけてあげましょう。 私も以前ピアノを習っていた時、一生懸命練習したのに弾き間違えただけで「練習してないのでは?」と努力を否定され、やる気をなくした経験があります。だからこそ、子どもには「努力は認める」という姿勢で接しています。
3. 親が「丸付け」をする
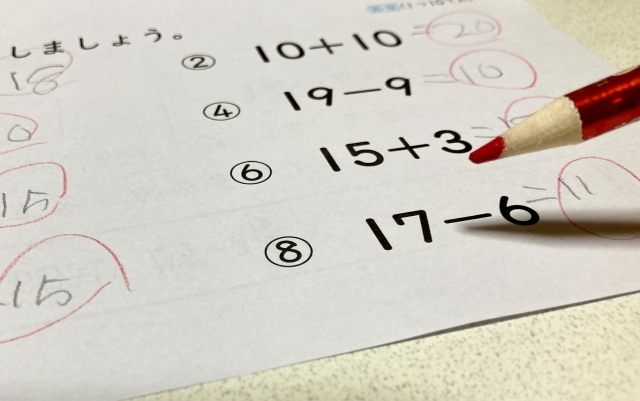
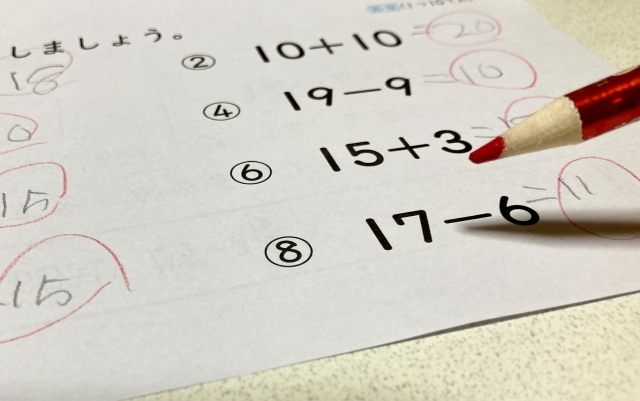
子どもの学習状況を把握するために、親が丸付けをすることをおすすめします。
子どもの理解度を確認できる
どこでつまずいているのか、どこを思い込みで間違えているのかなど、丸付けをすることで子どもの理解度を把握できます。
勉強時間を短縮できる
子どもが自分で丸付けをするよりも、親がやってあげることで、子どもは次の問題にすぐ取り掛かれます。これは、特に勉強時間が限られている場合に大きなメリットです。
我が家の長男は、小学生の頃はほとんど私が丸付けをしていましたが、中学生になると自然と自分でやるようになりました。お子さんの成長に合わせて任せていくのも良いでしょう。
家庭学習には「通信教育」も強い味方
ここまでの関わり方を試す中で、教材選びに悩むこともあるかもしれません。そんな時に心強い味方となるのが通信教育です。
特に進研ゼミは、子どもが楽しく取り組めるように工夫されています。カラフルなテキストやタブレットを使った学習は、我が家の子ども達が「宿題より先にやりたい!」と思うほど、意欲を引き出してくれます。
塾に通うのが難しいご家庭でも、質の高い教材と親のサポートがあれば、家庭学習だけでも成績アップは十分に可能です。ぜひ、家庭学習の環境づくりを一緒に見直してみませんか?